2025.11.18
紙幣も絵画も同じ視線で──不思議な広がりを持つ画家 クレマン・セルヴォー
昨年の夏、まとめて多くの絵画を買取させていただきました。その中にクレマン・セルヴォー(Clément Serveau, 1886–1972)の作品がありました。落ち着いた風景画で、最初は「上品だな」という程度の印象でしたが、調べていくうちに意外な経歴が見えてきて、興味が一気に深まったのを覚えています。
セルヴォーはフランス銀行の紙幣や、多くの国で使われる切手のデザインも手がけていました。キャンバスの上だけでなく、日常の中にある“お金”や“郵便”にもアートを届けていたと知ると、手元の風景画にもどこかデザイン的な視点が潜んでいるように感じられます。
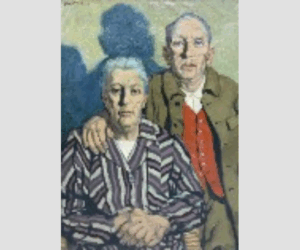
作風が大きく変わり続けるのに、不思議と通った一本筋
セルヴォーはパリの国立装飾美術学校で学んだあと、国立美術学校にも進みました。その後は裸体画や風景、肖像、静物など、さまざまなテーマに挑戦しています。油彩だけでなく、ガッシュやパステル、混合技法、フレスコ画にも取り組み、早くからジャンルにとらわれない自由な制作をしていました。
初期の作品は写実的で、現実の質感を丁寧に描いています。しかし時代の変化とともに、新しい表現に目を向けるようになります。特にルイ・マルクーシ(Louis Marcoussis)との交流は大きく、キュビスムの影響を受けるきっかけになったと言われています。幾何学的な構造や分割された形、ずれる視点など、セルヴォーはこうした実験を積極的に取り入れ、独自の構成感覚を育てました。
その後はポスト・キュビスム的な抽象表現へと進み、色や形を整理した、よりデザイン性の高い絵画を描くようになります。初期の写実から抽象への変化は大きいものの、どの時期の作品にも共通して感じられるのは「構成のうまさ」と「静かな調和感」です。セルヴォーの絵には、いつも整理された視線が流れています。

紙幣と切手のデザイン──芸術が日常に入り込む瞬間
1946年、師であるリュック・オリヴィエ・メルソンの紹介で、紙幣のデザインを任されました。紙幣は使いやすさや安全性も求められるため、絵画とは違う緊張感があります。しかしそこにほどよい装飾性と整った構図を取り入れる姿勢は、彼の画風と重なって見えます。
さらに1956年から1970年にかけて、セルヴォーはフランス国内外の切手を合わせて42枚制作しました。切手はごく小さな空間でデザインする必要があり、画家としての表現力だけでなく、デザイナーとしての論理的な整理力も求められます。セルヴォーの作品がデザイン的に洗練されているのは、こうした実用美術の経験が背景にあるからです。
また、公共アートにも積極的に取り組みました。国立美術学校ではフレスコ画科の指導にあたり、1937年のパリ万国博覧会では観光パビリオンの装飾も手がけています。絵画だけでなく、建築や教育、印刷物など、多様な領域で「芸術の生かし方」を広げていったのです。
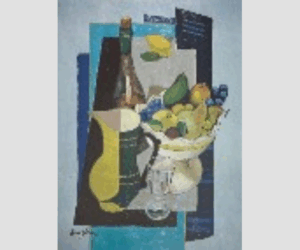
「変化」と「一貫性」を併せ持つ稀有なアーティスト
1936年にはレジオンドヌール勲章のシュヴァリエを受章し、海外での展覧会にも多く参加するなど、長く安定した評価を得て活動しました。晩年にはゆかりの地へ作品が寄贈され、展示室も設けられたことから、地域に根づいた存在でもあったことがうかがえます。
セルヴォーの作品を見ると、写実、キュビスム、抽象、紙幣デザイン、大型フレスコなど、さまざまなジャンルを軽やかに行き来していることがわかります。しかし、その根底にはいつも「形を整理する目」と「構成を整える手」があります。
作風が変わっても、芯の部分はぶれません。だからこそ、紙幣のような公共のデザインを任され、抽象画家として高く評価され、切手のデザインにも挑戦できたのでしょう。
ひとつの型に収まらず、表現の場を広げ続けたセルヴォーの作品は、生活の中にもアートが入り込めることを、静かに教えてくれているように思えます。
















